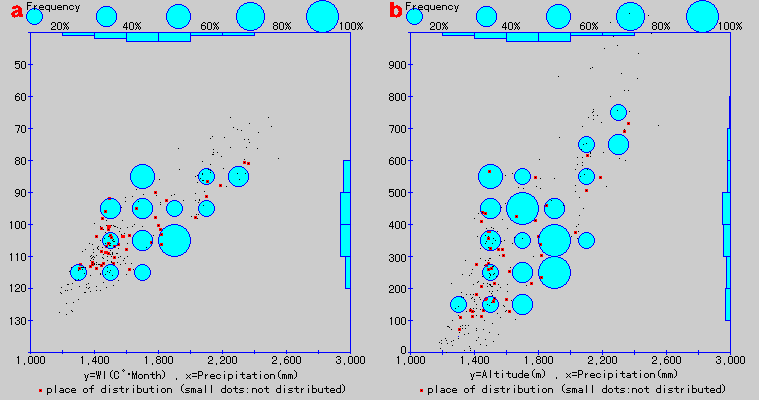
B1.典型的暖温帯上部の種 モミ・ウラジロガシ・アカガシ・シラカシ等
主に,WI80〜120℃の地域において分布が見られる種群である。
モミ(図16)
メッシュ気候値から推定した主要な分布域と実際の分布域を比較すると,県北西部の蒜山高原を中心とした地域で実際の分布が見られない。この原因については,地質・地形的な要因,或いは積雪条件等である可能性がある。
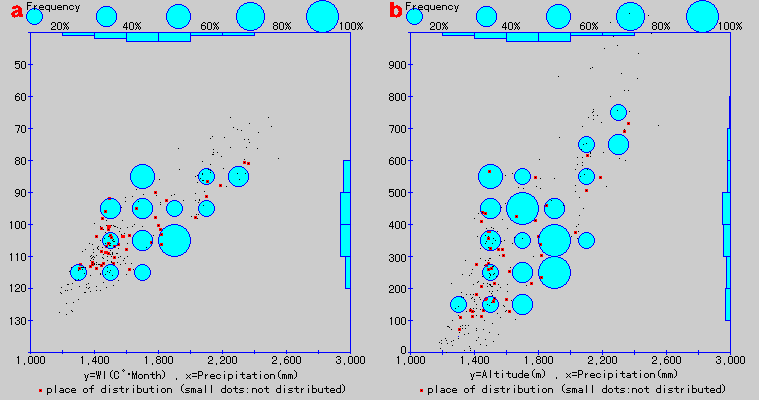
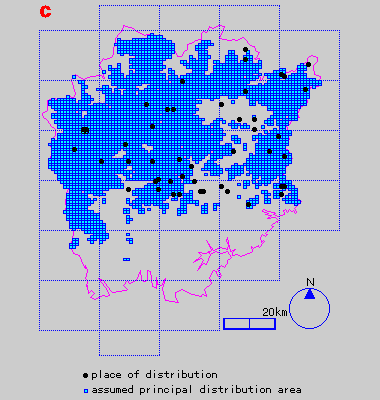
図16.モミ Abies firma
ナツアサドリ・タカノツメ・ツクバネウツギ・ナラガシワ・ウグイスカグラ spp.
モミ及びこれらの種は,概ね海抜100〜500m,年降水量1200〜2000㎜の地域を分布範囲としている。分布範囲の中では比較的コンスタントに見られ,暖温帯上部から中間温帯の二次植生或いは本来の植生を特徴付けるものと考えられる。
シキミ・シロダモ
暖温帯上部から中間温帯にかけての中間帯針葉樹林の標徴種であるが,この優占種であるモミと出現頻度の高い区間,及び北限域の分布傾向がよく一致している。
フジキ・ヤマブキ・ガンピ
WI90〜110℃,年降水量1600㎜以上の地域で,やや出現頻度が高い。フジキ・ヤマブキは,岡山県では吉備高原面を主な分布地としているが,ガンピに関しては低海抜地に分布中心がある。いずれも,露岩地・崩壊地等に生育する傾向がある種である。
シラカシ(図17)
WI90〜100℃の地域に分布の極大がある。また,海抜高度に関しては,300〜400mの地域にわずかな分布の極大があり,吉備高原面以北が主な分布地である。年降水量1600㎜以上の多雨地域では,低海抜地においても優勢であるが,1600㎜未満の低海抜地では,出現頻度が低下している。乾燥に対する適応性がアラカシ等の分布型A1等に比べて低いため,劣勢であるものと考えられる。
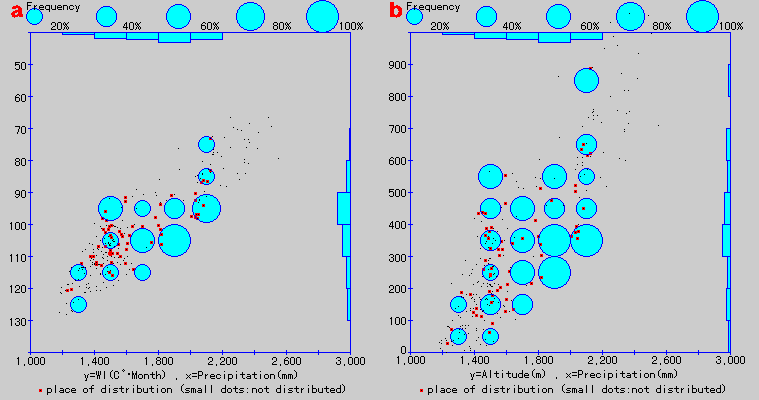
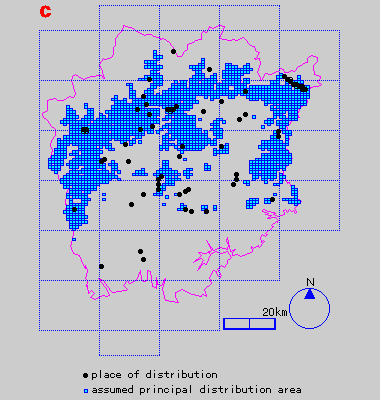
図17.シラカシ Quercus myrsinaefolia
カゴノキ
スダジイ(A4)よりも寒冷地まで分布を広げているが,海抜の極大はより低地となっている。年降水量でもより分布範囲が広いが,WI・年降水量における分布傾向は両種ともよく似ている。
ツガ・ウラジロガシ(図18)
WIに対する分布傾向はカゴノキと類似しているが,海抜では300m以上の地域に分布の極大があり,より高海抜地に出現する傾向がある。このような地域は,スダジイ・タブノキの分布地域と重複しているが,年降水量に対しては,スダジイ・タブノキの出現頻度が高い区間では劣勢で,スダジイ・タブノキが出現しない1800㎜以上の地域で出現頻度が高くなる。
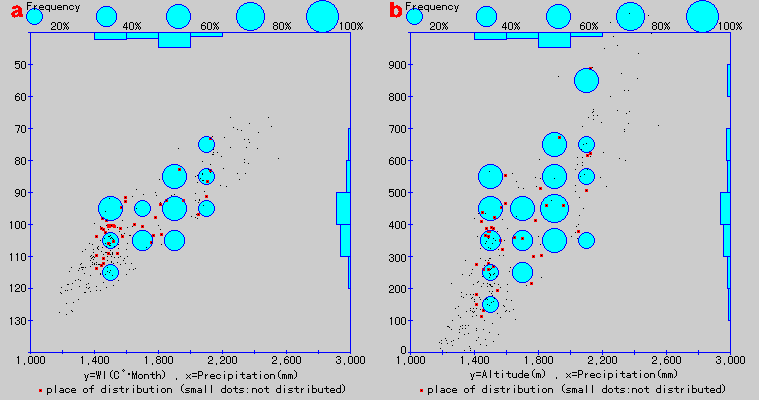
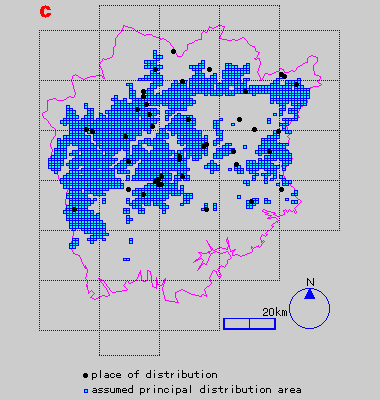
図18.ウラジロガシ Quercus salicina
海抜高度・降水量分布の傾向に関してはタブノキと類似性が高いが,本分布型の中では最も高海抜地に分布の極大を持っている。このような分布傾向は,山頂・尾根等の雲霧が発生する立地を分布の拠点としていることで説明されている(沼田ほか,1996)。
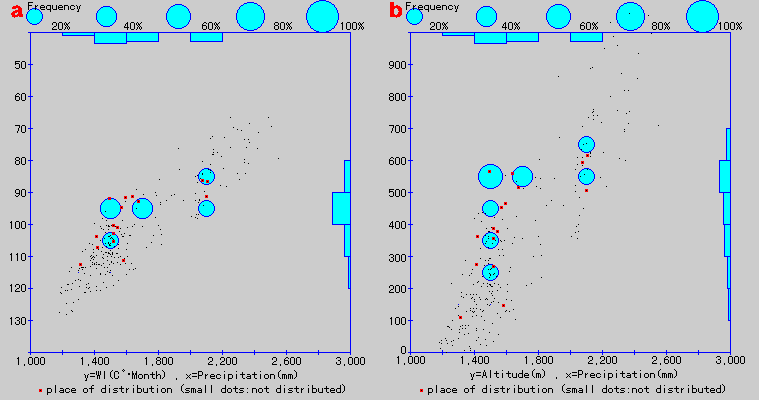
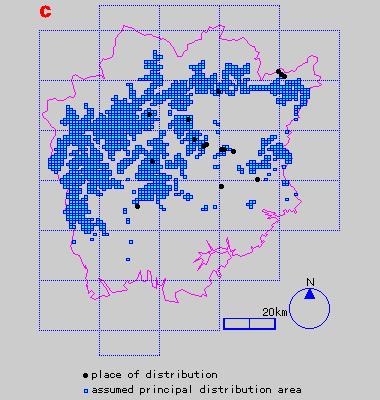
図19.アカガシ Quercus acuta
[最初のページ]・ [B.暖温帯上部の種]・ [B2.特異な分布を示す種]